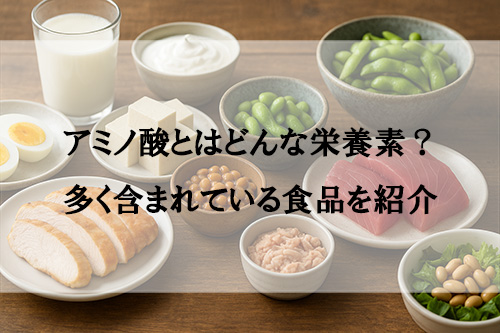
「最近疲れやすい…」
「筋トレの成果が伸び悩む…」
「食事だけで十分か不安…」
そんなお悩みに寄り添いながら、成分「アミノ酸」を基礎からやさしく解説します。必須アミノ酸・分岐鎖アミノ酸(BCAA)などの種類、体内での働き、摂取タイミング、食事とサプリの使い分け、安全性や注意点までを網羅。この記事を読めば、目的に合った選び方と摂り方の具体像がつかめます。
アミノ酸とはどんな成分?
アミノ酸は、たんぱく質を構成する最小単位で、筋肉・臓器・酵素・ホルモンなど体づくりの基礎になります。
体内で合成できない必須アミノ酸は食事からの摂取が必要。運動や成長期、食事量が不十分なときの栄養補助として注目されています。
目的に合わせた配合を選べば、たんぱく質摂取を補い、運動時の栄養サポートや日々のコンディショニング維持に役立ちます。
- 必須アミノ酸を効率よく補える
- たんぱく質摂取が難しい場面の栄養補助になる
- 運動前後の栄養設計がしやすい(BCAA/EAAなど)
過剰摂取や偏った置き換えは望ましくありません。食事の質を置き換えるのではなく、補助として活用しましょう。
- 過剰摂取は胃腸の不快感を生むことがある
- 味・甘味料が気になる製品もある
- 食事バランスを損ねると本来の効果を得にくい
アミノ酸の効果・効能
アミノ酸(とくに必須アミノ酸=EAA)は、筋たんぱく質の合成(MPS)に不可欠で、運動後の回復時にMPSを高めることが示されています。
中でもロイシンはスイッチ役として知られ、十分量を含むEAA摂取が高齢者のMPS刺激に有利という報告があります。
一方、BCAA(ロイシン・イソロイシン・バリン)単独は、筋損傷マーカーや筋肉痛の軽減に「小~中程度」の効果が示唆される一方で、効果の大きさや条件にはばらつきがあります(運動栄養の補助的選択肢)。
どんな人におすすめ?
食事でたんぱく質が不足しやすい場面の栄養補助、運動前後の回復設計、高齢期のフレイル予防を意識した質のよいたんぱく質摂取の後押しとして、EAAやBCAAを含む製品の活用が検討できます(まずは食事の見直しが基本)。
- 食事だけでたんぱく質量・質を満たしにくい人
- 定期的にトレーニングを行い、回復やコンディション維持を重視する人
- 少量高たんぱくを意識したい高齢者(まずは食品での確保が前提)
1日の推奨摂取量の目安
サプリ単体の「推奨量」設定はありません。まずはたんぱく質量で目安を確認します。日本の食事摂取基準(2025年版)では、成人の推定平均必要量=0.66 g/kg体重/日を用いて推奨量(g/日)が算出されています(下表)。なお、腎機能影響などの明確な根拠不足により耐容上限量は設定されていません。
日本人の食事摂取基準(2025年版)抜粋
| 区分 | 推定平均必要量(g/日) | 推奨量(g/日) | 目標量(%エネルギー) |
|---|---|---|---|
| 男性 18–29歳 | 50 | 65 | 13–20 |
| 男性 30–64歳 | 50 | 65 | 14–20(50–64歳) |
| 女性 18–29歳 | 40 | 50 | 13–20 |
| 女性 30–64歳 | 40 | 50 | 14–20(50–64歳) |
必須アミノ酸の平均必要量(成人・参考)
・WHO/FAO/UNU(2007)の成人1日必要量(mg/kg体重)
ヒスチジン10、イソロイシン20、ロイシン39、リジン30、含硫アミノ酸(メチオニン+シスチン)15、芳香族(フェニルアラニン+チロシン)25、スレオニン15、トリプトファン4、バリン26。
補足
食事からの完全たんぱく質(肉・魚・卵・乳、または大豆などを上手に組み合わせた植物性)を優先し、EAA/BCAAは不足を補う位置づけで
アミノ酸が含まれている食品
まずは食事から良質なたんぱく質を確保するのが基本です。
以下は日本で手に入りやすい食品の標準的な可食量あたりのたんぱく質量と、例として1日60gのたんぱく質目標を満たすのに必要なおおよその量(目安)です。※数値は一般的な食品成分表をもとにした概算です。
食品と含有量の目安
| 食品(標準量) | たんぱく質量 | 60g達成までの目安 |
|---|---|---|
| 鶏むね(皮なし)100g | 約22–24g | 約2.5人前 |
| まぐろ(赤身)100g | 約23–26g | 約2.5人前 |
| 鮭 切り身80g | 約15–18g | 約3–4切れ |
| さば 切り身100g | 約19–20g | 約3人前 |
| 豚ロース 100g | 約19–22g | 約3人前 |
| 卵 1個(M,50g) | 約6g | 約10個 |
| 木綿豆腐 150g | 約10–12g | 約5–6丁(150g換算) |
| 納豆 1パック(45g) | 約7–8g | 約8パック |
| ギリシャヨーグルト 100g | 約9–11g | 約6–7個 |
| 牛乳 200ml | 約6–7g | 約9–10杯 |
| ツナ缶(固形量70g/ノンオイル) | 約15–17g | 約4缶 |
| 鶏ささみ 100g | 約23–25g | 約2.5人前 |
| オートミール 40g(乾) | 約5g | 約12杯 |
| 玄米ごはん 150g | 約4g | 約15杯 |
動物性(肉・魚・卵・乳)は必須アミノ酸バランスが良好。大豆製品は植物性でも質が高く、動物性と組み合わせるとさらに◎。
おすすめの料理
高たんぱくで作りやすいのは、鶏むねの塩麹焼きや鮭の塩焼き、ツナと豆腐の和え物など。
朝は納豆+卵かけごはん+味噌汁(豆腐入り)で手軽に底上げ、運動後はギリシャヨーグルト+フルーツで素早く補いましょう。
脂質が気になる場合は蒸す・茹でる・焼く調理を中心に。
おすすめ料理とたんぱく質の目安
| 料理(1人前) | 主材料 | たんぱく質量 | メモ |
|---|---|---|---|
| 鶏むねの塩麹焼き | 鶏むね120g | 約27g | 下味でしっとり、作り置き向き |
| 鮭の塩焼き | 鮭切り身100g | 約19g | 朝食や弁当に◎ |
| 豆腐ツナ和え | 木綿豆腐150g+ツナ缶70g | 約26g | 火を使わず時短 |
| 納豆卵かけごはん | 納豆45g+卵1個 | 約13–14g | 朝の定番、海苔やしらすで強化 |
| ギリシャヨーグルトボウル | ヨーグルト150g | 約14–16g | 運動後の補給に |
アミノ酸に関するQ&A
- EAAとBCAAの違いは?
-
EAAは体内で作れない必須アミノ酸9種を含む総称、BCAAはその一部のロイシン・イソロイシン・バリンの3種です。食事で不足しがちな場合はEAA、運動時の補助にはBCAAも選択肢になります。
- 飲むタイミングはいつ?
-
基本は食事で十分量を確保しつつ、補助的に「運動前後」や「食間」に。空腹時は吸収が速い一方、胃腸が弱い人は軽食と一緒が無難です。就寝前は胃もたれしない量で様子見を。
- 一日の摂取量の目安は?
-
サプリの画一的な推奨量はありません。まずは体重1kgあたり0.8g前後のたんぱく質を食事で確保し、不足分のみEAAやBCAAで補う考え方が基本です。過剰摂取は避けましょう。
- プロテインとの違いは?
-
プロテインは牛乳由来などの“たんぱく質食品”で、消化してアミノ酸になります。アミノ酸サプリは最初から低分子で吸収が速い一方、満腹感や価格面ではプロテインに軍配が上がる場合も。
- 副作用や注意点は?
-
健康な方の通常量では大きな問題は稀ですが、過剰摂取は胃部不快や下痢の一因に。腎機能などに不安がある方、妊娠・授乳中、服薬中の方は利用前に医療専門職に相談を。
- ロイシンのしきい値は?
-
筋たんぱく合成のスイッチ役とされるロイシンは、食事1回あたり一定量以上を含むと効率が上がると示唆されます。まずは肉・魚・卵・乳・大豆など質のよいたんぱく質を十分量とるのが近道です。
- アミノ酸は高齢者に向いている?
-
加齢で食が細くなると、たんぱく質と必須アミノ酸が不足しやすくなります。まずはやわらかい肉魚や卵・乳・大豆で小分け摂取を。補助的にEAAを活用すると少量で質を確保しやすくなります。
- ダイエット中はどう使えばいい?
-
総エネルギーを落としつつ筋肉量を守りたい時は、1食のたんぱく質をしっかり確保するのが第一。間食にヨーグルトや卵、大豆を。食事で足りないときだけアミノ酸でピンポイント補給が合理的です。
- 空腹時の吸収は速い?
-
遊離アミノ酸は消化工程が不要な分、食事たんぱくより吸収は速い傾向。ただし速ければ必ず効果が高いわけではありません。総量と1回あたりの“質”を満たす食事設計が最優先です。
- 食品だけで十分にできる?
-
多くの方は、肉・魚・卵・乳や大豆製品を毎食に配して十分量を達成できます。忙しい時や食が細い時、運動直後など穴が出やすい場面だけサプリで補うと、コストと実効性のバランスが良好です。

